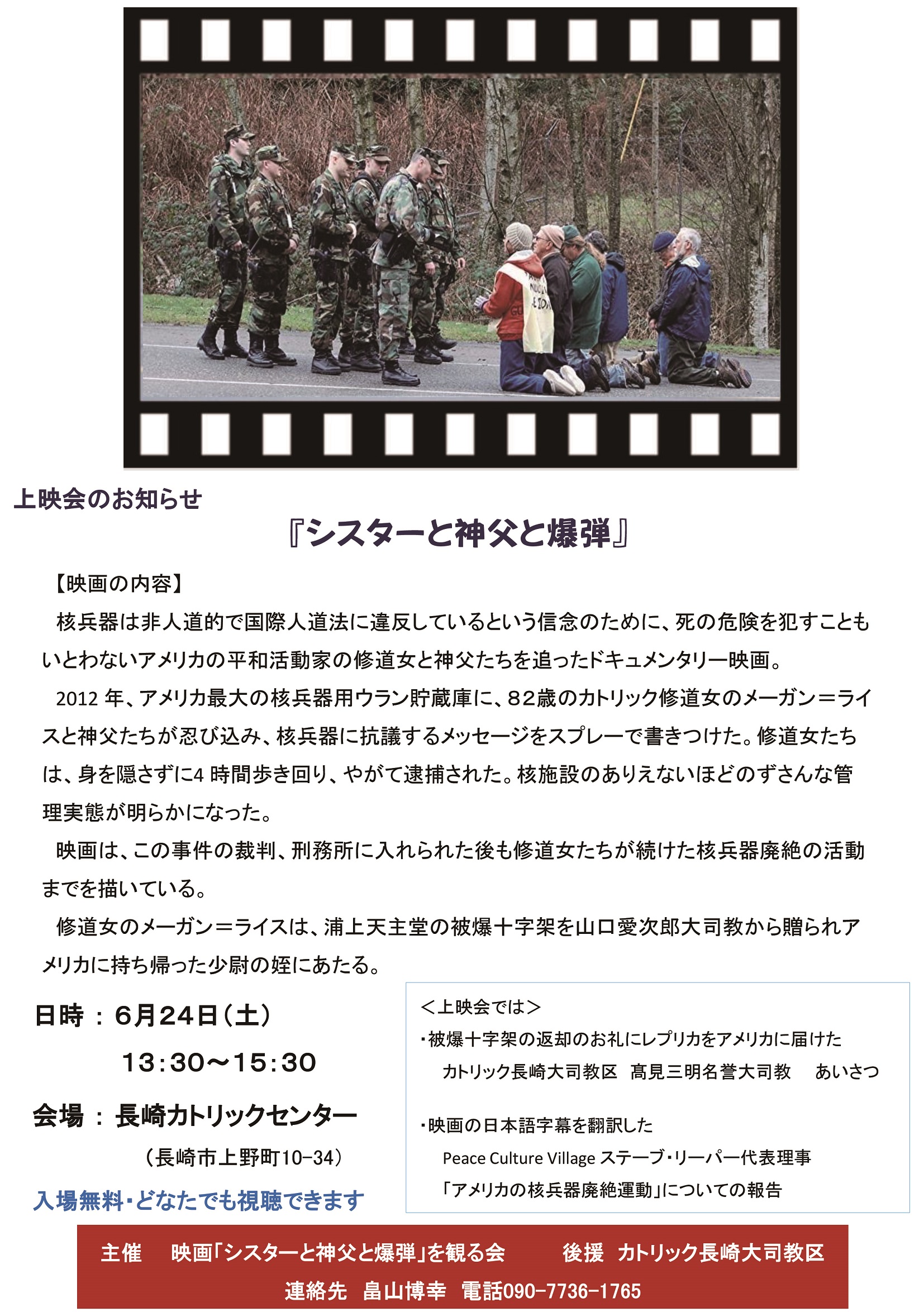【当日の映像】 長崎大司教区家庭委員会 YouTube で公開しています。
迎え入れ式と記念ミサ https://youtu.be/sD4JYP7hXik
説教 https://youtu.be/WuTss6YzW9s ( ← 2023年6月5日に追記しました。)
ロザリオ行列 https://youtu.be/rdJqfINHA2Y ( ← 2023年6月8日に追記しました。)
1枚目の写真:浦上教会を目指し、ロザリオを唱えながら徒歩巡礼する参加者
浦上四番崩れによって浦上信徒らが全国22カ所に流配された出来事、『旅』からの帰還150周年にあたる今年、長崎大司教区は 5月28日(日)にロザリオ行列と記念ミサを行った。
第1部は 11時50分の出発式に始まり、流配地の藩名を記したたすきをかけた22人の代表者らが、大波止から西坂公園に向けてロザリオ行列した。公園到着後は13時15分から、集まった人々が共に殉教者たちをしのび、浦上教会を目指してロザリオを唱えながら1時間以上をかけて徒歩巡礼した。
第2部は15時から浦上教会で、中村倫明大司教の主司式、広島教区の白浜 満司教、髙見三明名誉大司教、約20人の司祭団の共同司式のもと、記念ミサが行われた。ミサの最後に、代表者らから若い世代の人々へ「信仰のバトン」が受け渡された。
『旅』の終わり150周年を記念する行事は今後、7月23日(日)13時30分から浦上教会で高校生による演劇(『旅』からの帰還・岩永マキ物語)の上演と、9月10日(日)14時から十字架山で殉教記念ミサが予定されている。
( 『カトリック教報』2023年12月号 の掲載に合わせ 11月22日に編集済み)
2023年5月28日
旅からの帰還150周年記念ミサ 説教
「福音の香り」立つ長崎の教会へ
長崎教区司祭 古巣 馨
想い起こせば
「幼少のころ、祖母たちから聞いた『旅の話』を、私は今も心の奥底に大事にしまって居る。祖母たちは、囲炉裏の周りに集まると、それぞれの思い出を語り合うのであった。……寒中凍った池の中に、終日さらされたお話や、食物がなくてウジ虫を食べたお話など、今考えるとぞっとする様なむごいことも、その頃は『天主様のために堪え忍んだ』貴い功として、心地よく聞いたものである」
これは、1943年9月出版、浦川和三郎著『浦上切支丹史』の奥書を託された、片岡弥吉の文章です。旅からの帰還70年目、浦川司教67歳、片岡弥吉35歳の時です。「旅の話」が納められた『浦上切支丹史』は、大切なものを手渡し、しっかり受け取った人たちの証しです。浦上に原爆が投下されたのはこの2年後です。
繰り言のように同じ話をするのは、古き良き時代の美談や武勇伝を懐かしむためではありません。想い起こすと、力が湧いてくる話があります。想い起こすと、毎日のしんどさや、腐りかけた人生に、勇気と希望を与えてくれる話があります。想い起こすことから、記念は始まります。「これを、私の記念として行いなさい」(一コリント11・25)信仰は「記念する」ことです。キリストを想い起こし、今の生活に照らし、明日は顔を上げ、もっと良い人になろうと一歩踏み出すのが「記念する」ことです。
誠実な人の祈り
今年は、浦上と十数名の五島・伊王島の信徒を合わせ3384人が流罪とされ、金沢以西20藩・22カ所に流され、5年から3年におよぶ囚人としての苦難の生活から解放されて150年目です。この出来事を想い起こし、力と希望を得て、またオナジ心で歩み出さないと「記念」にはなりません。
ザビエルの宣教から今年で474年、日本の教会の歴史と静かに向き合い、そこに語られる神のみ言葉に耳を傾けると、長崎の教会は旧約のイスラエルの民と、キリストの十字架と復活を追体験するために、特別に選ばれた教会だと自然に手を合わせたくなります。
「神は本当にいるのか? いるのならば、なぜこんな惨めで、不条理な人生なのか? ここまでして、信仰は守らないといけないのか?」受けた大事なことを支えに生きただけで、「鞭打たれ、石を投げつけられ、故郷を追われ、…しばしば眠らず、飢え渇き、空腹と寒さに凍え、裸でいたこともありました」(二コリント11・23-29)福音のために苦労三嘆したパウロの呟きです。でも「誠実な人の祈り」に、神は必ず答えてくださいます。
捕囚の民の追体験
イスラエルの民は、二度、奴隷として異国に追放され「捕囚の民」となります。一度目はアッシリア、二度目はバビロンです。「流れのほとりに座り、柳に竪琴をかけ、シオンを思いすすり泣いた」(詩編137)のは、バビロン捕囚の時です。捕囚の民はたいてい絶滅して終わりました。「神などいない」と叫ぶ者に、「私はある、私は本当にある」とおっしゃるお方は、ときに、激しく歴史に介入します。「いかに美しいことか、山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は」(イザヤ52・7)「見よ、私は彼らを北の国から連れ戻し、地の果てから呼び集める。その中には目の見えない人も、歩けない人も…臨月の女もいる。彼らは泣きながら帰ってくる」(エレミヤ31・8-9)囚われ人への解放の福音と、帰国の途に就く人々の姿は、読むたびに胸があつくなります。長崎の教会も、「捕囚の民」の追体験へと招かれました。
1644年マンショ小西神父の殉教を境に、寺請檀那制度・宗門改めの中、教会は250年間、口をつむぎ、泥をかぶり、死んだふりをして最初の捕囚の時代を生きてきました。もう絶滅し、途絶えても不思議でないほどの時間が経っていました。でも、「人が忘れても、私はあなたを決して忘れない」(イザヤ49・15)と約束された神は、プティジャンを遣わし、沈黙の教会に「良い知らせ」を伝えてくれます。「ワレラノムネ アナタノムネト オナジ」
神のみわざに勢いづいた信徒たちは、まだ禁教令が続いているさ中、お寺への絶縁状を突き付けたのです。当時の英字新聞が報じたように、「明治政府の転覆をねらった宣教師の画策で、キリシタンに無謀な行動をとらせた」(1873年1月1日 The Times )のではありません。司祭到来は、潜伏という捕囚からの解放の知らせでした。その喜びから生まれた信徒たちの応えが寺請檀那制度との決別だったのです。
「国家神道」の御旗のもと、近代国家へと船出したばかりの明治政府は、財産も身分もない「キリシタンという長崎の田舎者」に、国造りの根幹を揺さぶられたのです。政府は「浦上一村総配流」の沙汰を下します。これが、2回目の捕囚「浦上四番崩れ」です。1868年6月と1870年1月の2回に分けて追放されます。
父と子のまなざし
2回目の追放のとき、大浦天主堂から3人の司祭が、その一部始終を見届けていました。秘密教会の一斉手入れの際、間一髪で逃げ延びたロケーニュとポワリエ、そして1868年10月に長崎に来たばかりのヴィリオンです。25歳の若きヴィリオンが目にしたのは、「信徒発見」のまばゆい奇跡の教会(マタイ17・2)ではなく、偏見と虐げが続く、いまだ、社会から見捨てられた、「孤独な水溜まりの教会」でした。
「信者たちはみな天主堂を仰ぎ見ている。十字架のしるしをする者もある。婦人たちはみな洗礼の時にかぶった白いヴェールを頭にいただいていて、信仰を公表している。何という光景! 1597年の26人の殉教者、さらに17世紀の幾千もの殉教者が行った信仰宣言を、その子孫たちによって今もなされている、この勇敢な信仰宣言を、私は今、港の奥から眺めているのだ」(ヴィリオン『日本宣教50年』)この日のヴィリオンの日記です。そのページには幾筋もの滲んだ涙の跡があったに違いありません。
母マリアがそこにいた
ヴィリオンは信徒たちを見送ったあと、すぐに神戸に移り、離散した信徒たちの安否を確かめて回っています。飢えと寒さ、すし詰めの悪臭漂う生活を堪える信徒に、司祭たちは涙します。信徒は、どんなときも、自分たちに思いをよせる司祭のまなざしを探します。「もうどうでもいい」と思うほど辛く、折れそうなときも、独りではありませんでした。隣には、いつも祈りながら一緒に歩く家族や仲間と、イエスの十字架のもとから遣わされた母マリアが共にいました(ヨハネ19・26)。信徒と司祭がオナジいのちの方角を向いていたのです。
気骨ある人の従順によって
3年後、欧米諸国の非難と信徒を預かった諸藩からの苦情、そして、どんなに国家権力で脅され、折檻され、家族や仲間の非業の死を前にしても、決して屈せず、背中に一本筋の通った信仰をもつ「無知な田舎者」と侮った信者に、明治政府はついに根負けしました。秀吉から数えて286年続いた「キリシタン禁制の高札」を撤去し、「長崎県下異宗徒帰籍」を発布します。虫けらのように扱われても、受けた教えを誠実に生きる人たちを目の当たりにした為政者は、その16年後、1889年2月、「大日本帝国憲法」第28条で、「他人の迷惑にならない限り」という条件付きながら、「信教の自由」を保障したのです。気骨ある人たちの捧げた命と苦しみが、日本のすべての人たちに、「心の自由」という「実り」をもたらしました。
よい便りを伝える人の足
やがて、捕囚の民の帰還が始まります。「声を響かせ、賛美し…泣きながら」(エレミヤ31・7-9)神戸教会を目指した人の数は、同年4月22日の記録で2千人に達しています。
でも、5年から3年におよぶ飢えと渇き・氷点下の寒晒し・劣悪な牢生活は「誠実な残りの者」(ローマ11・5)の、帰郷の喜びさえ蝕んでいました。神戸や大阪に辿り着けず、まだ遠くの道端にうずくまったり、行き倒れて息絶えた人を道わきに葬ったりしている人たちがいると聞くたびに、ヴィリオンや大阪のクザンは、近隣の人力車や大八車をすべて借り上げ、総動員で迎えに走ります。解放されたからといって、「小躍りし、賛美の歌をうたいながら、勇んで戻る力」はもうなかったのです。でも、このときも、身を引きずりながら歩く信徒と、抱き起こし、支えて歩く司祭は同じ方向を向いていました。
追放された3384人のうち、亡くなった者613人、折檻と保身のため信仰を隠し1年前に戻った者1022人。そして、最後まで堪え忍び満身創痍で帰郷した「誠実な残りの者」1930人。待ち受けていたのは「お帰りなさい」という、労いや称賛の拍手とは無縁の、略奪と打ち壊された家、藪に覆われ、荒廃した畑地。慰めてくれるはずの故郷は見るも無残でした。最後まで堪え、帰還した1930人のうち「家のある者」1164人、「家のない者」766人と県の公文書に記録されています。
これが、帰還した教会の「新たな旅」の始まりでした。空腹と野ざらしの生活は、まるで流配地のようでした。このときのプティジャン司教の手紙を、フランシス・マルナスは『日本キリスト教復活史』に書き留めています。「政府は彼らの援助を約束しましたが、なかなかやってくれません。でも、彼らの兄弟である島々や近在のキリシタンが深い思いやりをもって、助けています。本当に立派です」
再び、オナジムネになるために
帰還した教会には、越えなければならないもう一つの大きな課題がありました。信仰を隠し一足早く戻った者たちと、「誠実な残りの者」たちの生活の格差と軋轢、そして反目。旅する教会の脆弱さが、痩せこけた人のあばら骨のように浮き出てきたのです。受けた体の傷よりも、狡猾さと裏切りによる心の傷はもっと根深く、やっかいでした。仮聖堂で一緒に祈っても、帰り道、挨拶の一つも交わせない。250年間、受け渡された「オナジ信仰」が試されました。傷ついた羊の痛みは、牧者の痛みです(教皇フランシスコ『福音の喜び』24)。主任司祭プトーが、辻町の丘に十字架山を建立したのは、赦しと和解の恵みがなければ、この教会は「新たな旅路」にも就けないし、「オナジ」信仰を手渡すこともできないと思ったからです。「憎しみや疑いを、愛と信頼に変えるのが、私どもの仕事です」(ヴィリオン前掲)ヴィリオンの言葉です。
ゆるしの恵みに応えて
こうして、皆でキリストの十字架のもとにひざまずき、赦しと和解の恵みに与った浦上は、また「オナジ」を生き始めていきます。赤痢や天然痘で倒れた人たちを介護し、親を亡くし、置き去りにされた孤児たちを抱き寄せ、「道端の隣人」(教皇フランシスコ『兄弟の皆さん』)になった教会は、長崎の町の「地の塩、世の光」(マタイ5・13-16)となりました。受けた信仰の真ん中にあった「慈悲の所作」は、赦しと和解の恵みへの応えです。出津のマルコ・ド・ロ、奥浦のマルマン、鯛之浦のブレル、天草のフィリエ。信徒たちは、慈悲の心を抱えて奔走する司祭の後に従い、どんな苦労があっても、ケラケラ笑いながら、「オナジ」わざを生きてきました。このとき、旅する長崎の教会は「福音の香り」(教皇フランシスコ上掲)を放っていたに違いありません。
「解放からの帰還」50年目、信徒たちとジャン・クロード・コンバス司教は、献堂したばかりの浦上天主堂の前庭に、『信仰之礎』の記念碑を据え、捕囚の民の出来事を忘れず、信徒と司祭と司教がオナジ方向に向かって旅することを誓ったのです。このとき長崎教区の信者は、ちょうど今と同じ5万5千人ほどを数えています。
「福音の香り」立つ旅路へ
あれから150年、長崎の教会は今、目まぐるしく変わる世の中で、「地の塩・世の光」になっているのでしょうか。どこを向いて、教会は旅しているのでしょうか。信徒と司祭と司教がオナジ方向を向いているのでしょうか。バラバラだと旅ではなくて、放浪です。「ワレラノムネ アナタノムネト オナジ」
(1)親たちが命がけで手渡した信仰の続きを生きること、(2)みんなで〝オナジ〟キリストの方角に向かって共に旅すること、(3)「福音の香り」立つ教会になること、これを150年目の「解放の記念日」の決意にしましょう。