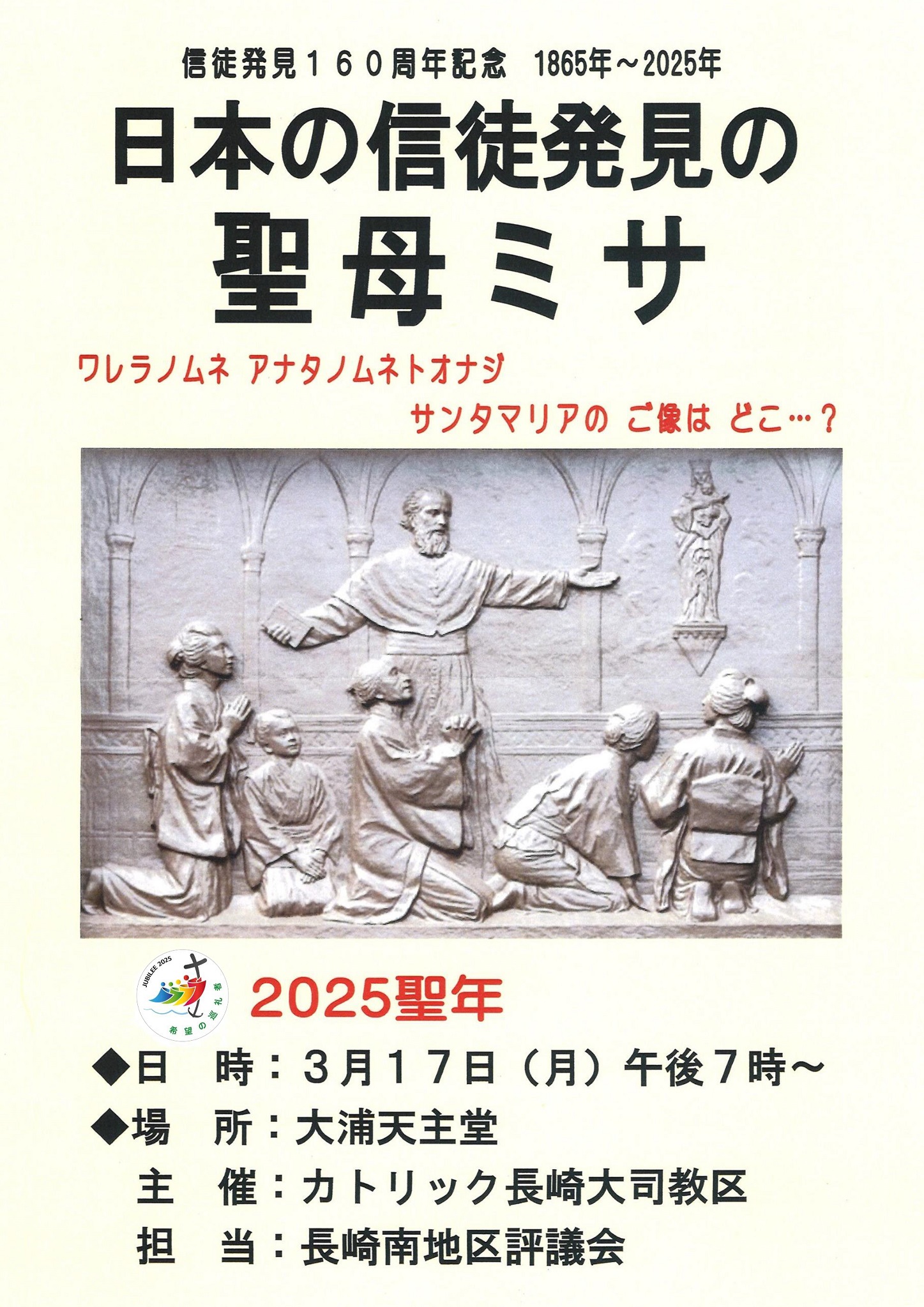【当日の映像】 長崎大司教区家庭委員会 YouTube で公開しています。
日本二十六聖人殉教記念ミサ https://youtu.be/JFAeZik1VPQ?feature=shared
( ↑ 2025年2月17日に追記しました。)
日本の教会は2月5日を、日本二十六聖人殉教者(聖パウロ三木と同志殉教者)の祝日として記念している。この日を前に2月2日(日)、長崎大司教区は14時から西坂公園で殉教記念ミサを行った。中村倫明大司教が主司式を務め、髙見三明名誉大司教と約50人の司祭団が共同司式をし、各地から集まった約1500人が殉教者を思い、祈りをささげた。(写真はミサの様子)
2025年2月2日、西坂公園での日本二十六聖人殉教記念ミサの説教(要旨) マタイ28・16~20
共同体としての26聖人
日本二十六聖人記念館館長 デ・ルカ・レンゾ神父(イエズス会)
私たちは26聖人一人一人のことを覚えるために「ルドヴィコは一番若い」とか「ヤコブ喜斉は一番年寄り」など、個人的な特徴を使います。しかし、彼らはグループ、強いて言えば共同体だったことを忘れてはいけません。
彼らは普段だったら生涯、一緒になることがなかったでしょう。五島、長崎、神戸、京都などの出身、侍の子どもだったパウロ三木とともに、当時の社会で名前も持たせてもらえなかったアントニオなど、考えてみればバラバラのグループでした。それに、残念なことですが、当時イエズス会とフランシスコ会は仲が良くなくて互いに批判し合っていました。おそらく、このグループに加わった修道士は、一緒に住んだこともなければ、一緒に宣教することもありませんでした。最初はできれば一緒にされたくない気持ちがあったでしょう。彼らは最初から一緒に宣教していた26人ではありませんでした。京都を出発した時、24人だけが処刑される予定でした。フランシスコ吉とペトロ助次郎は途中で加わったことが知られています。ペトロ・ゴメスの記録によれば、彼らは「我らは飛び入りです」と言って加わり、役人も周囲の人々もやめさせようとしたが彼らは「飛び入りです」と言って最後まで一緒になりました。
さまざまな史料を見ますと、強制的に集められた彼らは、長い道を歩きながら、互いの違いより共通点を見いだすことができました。長崎に近づいた時に互いの赦し合いを願ったり、一緒にミサに参加したいと願ったりしました。共に殉教に向かって歩む者としての自覚を養ったと解釈できます。
彼らの姿勢は現代の私たちに問いかけています。自分、あるいは「自分の国は先だ」と言いながら「他者と違う」と強調されます。長崎に着いた26聖人は、仲の悪いグループに属する相手、社会が差別する相手、であっても同じキリストへの愛によって共同体を作りました。私たちは同じ家族、同じ教会のメンバーと一緒になれないはずはないとの教えです。彼らの秘訣は何だったでしょうか。それは神から与えられた使命を果たすことにおいて共同体を作ることだったと思います。それは共に巡礼することによって自分たちだけではなく、イエスも一緒に歩んでいることを体験したからではないでしょうか。
いくら年齢、国、時代が異なってもイエスと共に歩むとすれば、違いを乗り越える共同体になれますように殉教者たちに祈りましょう。
最後に誤解がないように少し話させてください。最近、迫害されると感じる人や団体が増えています。確かに、世の中に苦しみや迫害はたくさんあります。しかし、私たちが模範とする殉教者は単に迫害された人々ではありません。私たちが祝う殉教者はイエス・キリストのために迫害と死を甘んじて受けた人々に限ります。それ自体神様からの恵みがなければ誰も成し遂げられないことです。国のため、人のために命を捧げる人を、キリシタンの殉教者とはされませんのでそのことを心にとめてください。おそらくこれについて聞かれることがあるでしょうから、はっきりと答えられますように備えてください。誤解を避けることも福音宣教です。
(説教ここまで)
また、記念日当日の2月5日には、長崎南地区司祭団が主催する「連続ミサとゆるしの秘跡」が西坂の聖フィリッポ教会で行われた。朝の9時から2時間おきに計6回のミサがささげられ、西坂の丘を訪れる人々の姿が終日みられた。